老後の住み替え、孤独死に備える高齢者の住まい
2022-10-31老後の戸建て暮らし
みなさんは集合住宅、アパート、戸建て、どれにお住まいでしょうか。
内閣府の「令和3年版高齢社会白書」では、現在65歳以上のかたの8割は持ち家という結果が出ています。かつて、都心や郊外に小さいながらも一戸建て「マイホーム」を持つことが大きなステータスだった時代がありました。
老後の戸建て暮らし、住み替えをしない選択肢ももちろんありますが、不安や懸念点があるとしたら、以下のような点ではないでしょうか。
- 身体的負担の増加
高齢者が一人暮らしになると身体的な負担が増えます。例えば、階段の上り下りや庭の手入れなど、日常の家事や維持管理が大きな負担になることがあります。特に、一戸建てでは敷地が広い分、居住空間だけでなく庭などのメンテナンスの必要もあり、高齢者の力だけでは補えない部分が出てきます。
- 防犯面の不安
戸建ては集合住宅と比べて防犯対策が各所有者にゆだねられているため、一人暮らしでみまもりシステムなどの導入もない場合は危険度が上がってしまいます。また、高齢者の一人暮らしで社会とのつながりも薄れて孤立した場合、セキュリティ面に対する注意力や対応が遅れることも懸念され、空き巣や泥棒や訪問販売などに対する不安も増えると言えます。
- 地域コミュニティとの関係性の希薄化
高齢者が一人暮らしをする場合、近隣住民とのつながりが希薄になり社会から孤立、孤独感も増して緊急時の支援が受けにくくなる可能性があります。地域に高齢者が減っていき、若い世代が周囲に増える場合、共通の話題が少なくなることで社会から高齢者が孤立するといったリスクもあります。
- 交通や買い物の不便さ
若いころに戸建てを購入する場合、ほとんどが郊外の静かな地域である場合が多く、そのまま住み続けていると高齢者になって車の運転が難しくなることが懸念されます。特に郊外のベッドタウンなど公共交通機関が不便な地域での一人暮らしは、買い物や病院への通院が困難になることがあり、特に病院やスーパーが近くにないと高齢者の一人暮らしの場合は日常生活に支障が出やすいです。
- 災害時の対応
高齢者の一人暮らしは地震や台風などの自然災害に対する備えが重要になってきます。特に高齢になると迅速な避難が難しくなるため、災害時の対応能力が低下して孤立するリスクも考えられます。
- 老朽化した住宅のメンテナンス費用
戸建て住宅は年月とともに老朽化していくため、定期的なメンテナンスが必要です。屋根や外壁の修理、設備の交換など、老後に大きな出費がかかる可能性があり、これが高齢者に経済的な負担になることがあります。
こうした住まいの不安や懸念点を解消するために、事前に現在の住まいにバリアフリー対応を行ったり、地域との関わりを積極的に持つ、防犯対策やメンテナンス計画を立てておくなど、老後に戸建てで暮らしても負担が少ない、また孤立しない、孤独にならない、といった安心して暮らせる対策を行うことが重要です。
ー70代から備える。老後を健康に過ごすために60代、70代から心がけることとは
ー心配するよりまず予防。70代、80代に向けた日々の暮らしとフレイル予防
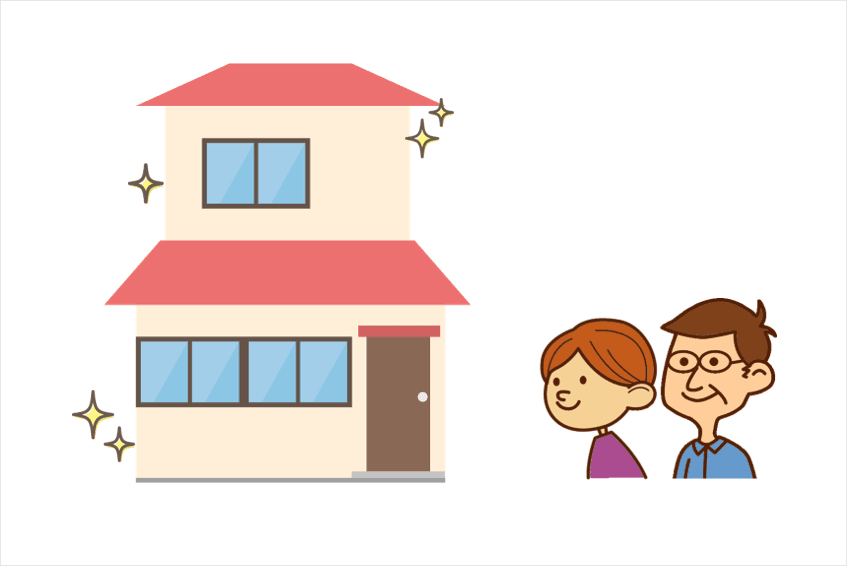
「一生の住まい」「子供たちに資産を残す」など大きな想定で建てた我が家も、その後に子世帯が自立して高齢夫婦だけになり、若いうちは苦にならなかった広さや階段、戸建てでの暮らしの維持と管理に苦労する例は少なくありません。
管理や利便性などでもう少し手狭なところに引っ越しをしたい、有料の介護付き施設を考える、2世帯や3世帯など家族と同居でも住宅設備が合っていないなど、老後の住まいについて考える必要は誰でも必ず出てきます。
元気なままで老後を迎えても、病気になったときどうするか、ご夫婦で老々介護になったらどうするか、など心配から気持ちが落ち込み、不安になってしまうこともあるかもしれません。
老後をできるだけ健康に、何かあっても安心して暮らせる住まいを選ぶことは実はとても大切なことなのです。
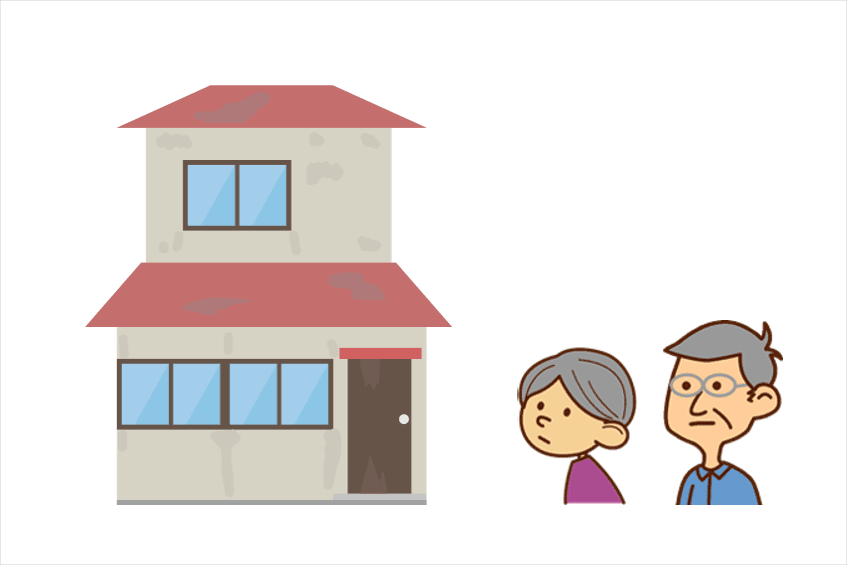
老後の住まいに集合住宅を選ぶメリット
老後の住まいに集合住宅を選ぶ高齢者が最近とても増えています。
セキュリティ設備や管理人が常駐している場合、緊急時に迅速に対応できる環境が整っており、一人暮らしの孤立しがちな状況でも安心感を得られるため、家族や本人にとっても心の支えとなるでしょう。
集合住宅ではバリアフリー設計がされていることが多く、エレベーターや段差の少ない設計は、体力や動きが低下している場合でも生活しやすいため高齢者に優しい環境が整っていると言えます。
また同じ建物に多くの人たちがいるため、住民同士の交流が生まれる可能性もあり、共用スペースでイベントが催されることもあるなど、孤独感が軽減され、社会的なつながりを保つのにもとても良い環境です。
もう一点、集合住宅のメリットは見守りサービスや生活支援サービスを利用できる住宅が増えていることも上げられます。日常的なサポートを受けられることが多く、医療や介護サービスが併設されている場合、将来的な健康リスクにも柔軟に対応できて安心です。
こういった点からもサ高住だけではない選択肢として集合住宅が選ばれる理由がわかります。
老後の住まいとして集合住宅が選ばれる理由を詳しくご紹介します。
- 安全面での安心感
集合住宅では防犯設備が整っていることが多く、外部からの侵入リスクが低いです。また、近隣住民がいることで緊急時に助けを求めやすく、孤独感や不安感を軽減することができます。
- 生活サポートが充実している
老後向けの集合住宅には、食事サービスや家事代行、医療ケアが提供される場合があり、日常生活のサポートを受けられるため、自立した生活を維持しやすくなります。
- コミュニティの形成
同年代の住民が多く住んでいるため、自然に交流が生まれ、孤立感を感じにくくなります。趣味やレクリエーション活動を通じて人とのつながりが得られることで、精神的な健康も保たれやすいと言えます。
- バリアフリー設計
高齢者向けに設計された集合住宅は、段差が少なく、エレベーターや手すりなどのバリアフリー設備が整っており、体力の衰えた高齢者でも、住まいとして安全に移動や生活ができる環境が整っています。
- コストの軽減
集合住宅の場合、一戸建てと比べて光熱費や維持管理費が抑えられることが多いです。また老後特化型の集合住宅では、管理費やメンテナンスの負担が少なく、住まいとして経済的な安心感も得られます。
老後において安心で快適な暮らしを送ることができる点が、集合住宅に住む大きなメリットです。
老後の住まいの考え方とポイント
住み替えで一番考えることは住まい(住宅)を変えることと、「住む地域を変える(別の地域で暮らす)」ことではないでしょうか。定年退職し、今までよりも家にいる時間が長くなる老後は、地域とのかかわりが増え、そのエリアの特性がとても重要になってきます。
戸建てを離れて住みやすい集合住宅にご夫婦で暮らす、一人暮らしなどにしても、高齢者が物件を探すことは孤独死や保証人など、様々な問題からとても困難です。
高齢者向けの物件を多く持っている管理会社を探す、独居でも安心の見守りサービスを設置した物件を選ぶ、地域包括ケアが充実しているエリアを選ぶ、など老後を安心して暮らすための方法は様々です。
戸建てや集合住宅に限らず、老後の住み替えは以下のポイント7つを意識するとよいでしょう。
バリアフリー設計
高齢者にとって、家の中の段差や狭い通路は転倒などのリスクが高まります。そのため、バリアフリー設計が施された住まいは非常に重要です。
段差をなくす、手すりを設置する、床が滑りにくい素材を使う、玄関やトイレ、浴室を広くするなどの工夫と、さらに車椅子や歩行補助器具を利用する可能性も考え、出入口や廊下の幅を広く設計するとよいでしょう。
安心できる見守り機能
高齢者が独居で生活する場合、孤立感や突然の体調不良、最悪の場合は孤独死などが懸念されます。そのため、見守り機能が備わった住まいだと安心です。
スマートホーム技術を活用して、センサーやカメラを設置し、異常が発生した際に家族や介護サービスがすぐに対応できるようになっている住宅が最近では増えています。
特に安否確認アプリや、夜間の見守りができるシステムを導入したり、見守りサービスの利用も安心です。
ケア付き住宅
高齢者専用のサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)やシニア向けの集合住宅は、ケアが受けられることが特徴です。これらの施設は、介護や医療サービスが提供されることが多く、健康状態に応じたケアが受けられ孤独死の心配もありません。
また、入居者同士の交流が促進され、孤立しにくい環境が整っています。入居者が同年代であることから、共通の話題が見つけやすく、社会的なつながりが保たれやすいというメリットもあるため最近ではとても人気です。入居待ちのところも多いため、早めに情報を集めておくこととよいでしょう。
利便性の高い立地
高齢者にとって病院や薬局、スーパー、公共交通機関などが近くにある利便性の高い立地の住まいを選ぶことも重要といえます。スーパーや薬局は特に日常的に利用するため、それほど遠くない位置にあると安心です。
徒歩や公共交通機関で日常生活に必要な場所へ簡単にアクセスできる場所に住むことで、自立した生活を維持しやすくなり、また緊急時に迅速な対応が可能になります。
コミュニティの充実
老後の生活では、周囲とのつながりが孤独を防ぐために不可欠です。地域のコミュニティやシニア向けのサークル活動が活発な場所に住むことで、日常的に人と接する機会を持つことができます。
また、住民同士の交流を促進する共用スペースが設けられている住まいも増えており、孤立感を感じにくい環境が整っています。
たまに人と会って話をする程度の付き合いから、積極的に社会と繋がれるような活動に参加することで孤立や孤独死を防ぐことができるようになります。
安全性とセキュリティ対策
高齢者にとって安心できる生活を送るためには、防犯面も重要です。
オートロックシステムや監視カメラなどの防犯設備が整っていることに加え、夜間でも安心して生活できる照明や、緊急時にすぐ連絡できる緊急通報システムの設置がおすすめです。
持続可能な家計管理
住まいを選ぶ際、生活費や家賃のコストも重要な要素です。固定収入の中で無理なく暮らせる住まいを選ぶことが、長期的に安心して暮らし続けるためには欠かせません。高齢者向けの公的支援や補助金、年金制度をうまく活用することで、経済的負担を軽減できる場合もあります。
こういった要素を総合的に考慮した住まいを選ぶことで、高齢者は健康で安心な生活を送りやすくなります。また、社会的なつながりを保ち、孤立や孤独死のリスクを軽減できる環境を整えることができるようになると言えます。
ー心配するよりまず予防。70代、80代に向けた日々の暮らしとフレイル予防
ー高齢の親の見守りを始めるきっかけ「フレイル」と「サルコペニア」
老後の住まい探しの懸念点
老後の住み替えにおいて一番の懸念点は、多くの場合「経済的な負担と長期的な資金計画の不安」です。
住み替えには引っ越し費用、物件購入や賃貸契約にかかる初期費用、場合によってはリフォームやバリアフリー改修などの追加コストが伴います。特に年金生活に入っている高齢者にとっては、限られた収入の中でこれらの費用を賄う必要があるため、資金不足や将来的な生活費の不安が大きな課題となります。
健康状態の変化への不安
住み替え先が今の健康状態には適していても、将来、身体能力や健康状態が変化した際にその住まいが対応できるかという不安があります。介護が必要になった場合に対応できるか、病院や介護施設へのアクセスが十分かといった点が懸念されます。
新しい環境での適応
長年住み慣れた場所から新しい環境に移ることは、特に高齢者にとって心理的負担が大きくなることがあります。近隣との関係や新しい地域社会への適応が難しいと感じる場合、孤立感が強まり、精神的なストレスが増す可能性があります。家族や支援者との距離
住み替えを検討する際、家族や支援者との物理的な距離が増えることで、緊急時に頼りづらくなる、日常的なサポートが減るといった懸念が生じます。特に介護や見守りが必要な場合、近くに頼れる人がいないと不安が増します。老後資金の減少
住み替えのために持ち家を売却したり、貯金を切り崩したりすることで、老後の生活資金が減少することも大きな懸念材料です。特に医療費や介護費用など、予測しづらい出費が今後増える可能性がある中で、資金の枯渇は避けたい問題です。将来の再度の住み替えのリスク
一度住み替えたとしても、さらに健康状態が悪化したり介護が必要になった場合に、再度の住み替えが必要になる可能性があります。これは体力的にも経済的にも大きな負担になるため、先を見越した住まい選びが重要ですが、その選択が難しいと感じる人も多いです。
これらの懸念点を考慮した上で、しっかりとした資金計画や健康管理、地域のサポート体制などを確認し、慎重に住み替えを検討することが重要です。
「老後の住み替え、孤独死に備える高齢者の住まい」まとめ
老後は自然豊かな郊外でのんびり暮らしたいと考える方が増えている一方で、「はじめて暮らす土地での不安」を感じる方も少なくありません。
まずは住まいを希望する地域での「地域包括ケアシステム」を調べることが重要です。
厚生労働省は、2025年(令和7年)を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとに、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。
地域包括ケアシステムとは、人口減少社会における介護需要の急増という困難な課題に対して、医療・介護などの専門職から地域の住民一人ひとりまで様々な人たちが力を合わせて対応していこうというシステムです。
要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで続けることができるように地域内で助け合う体制のことで、地域包括ケアシステムは、それぞれの地域の実情に合った医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される体制を目指しています。
「毎日」知りたい家族のサイン。
見守りアプリ「ピースサイン」は「毎日の見守り」と「地震などのいざという時の安否確認」両方の機能を搭載した見守りサービスです。高齢者にも使いやすい直感的なUIだから、面倒な操作方法によるわずらわしさからの「使わずに放置」の心配もありません。
\ピースサインとは/
離れて暮らす家族の体調が「毎日」わかる見守りサービスです
◆毎日同じ時間に届く通知にタップでお返事するだけ
◆簡単操作で、テキストを打ったり電話が繋がらないなどの精神的ストレスを軽減します
◆スマートフォンで手軽に始められて、機器の購入もありません
◆地震などのいざという時でもボタンひとつで安否確認
◆いざという時(未応答時)はGPS機能で居場所がわかるので安心
「記事タイトル」の関連記事はこちら
Peace Signが選ばれる理由

高齢の親と離れて暮らしていると、傷病発生、ヒートショック、熱中症、認知症など心配になる場面がたくさんあると思います。そんな時は見守りサービスの検討が必要です。数多く存在する見守りサービスの特徴と比較し、自分たちにあった見守りサービスを選ぶ事をおすすめします。「見守りサービスとは?」、スマートフォンアプリやセンサー設置するもの、人が訪問するものまで、わかりやすくご紹介します。またその中でアプリ型見守りサービス「ピースサイン」が選ばれている理由をお伝えいたします。
高齢者の一人暮らしはどのくらいで限界?発生する問題と解決支援サービスとは
2022-05-24

病気や介護、災害など一人で対処の難しい状況になったときにだれでも利用できるサービスの提供と「つらくても治療を受けて病院で生きる」生活から「自分らしく納得のいく生活」を目指す「QOL」に目を向けたサービスの実現に各自治体と企業で取り組んでいます。
高齢者見守りサービス・安否確認サービス、全国自治体(東京都・大阪府)の取り組みとは 【自治体別、高齢者見守りサービス】
2022-05-24

高齢者見守りサービス・安否確認サービス、全国自治体(東京都・大阪府)の取り組みについて東京、大阪を中心にまとめました。
関連タグ




